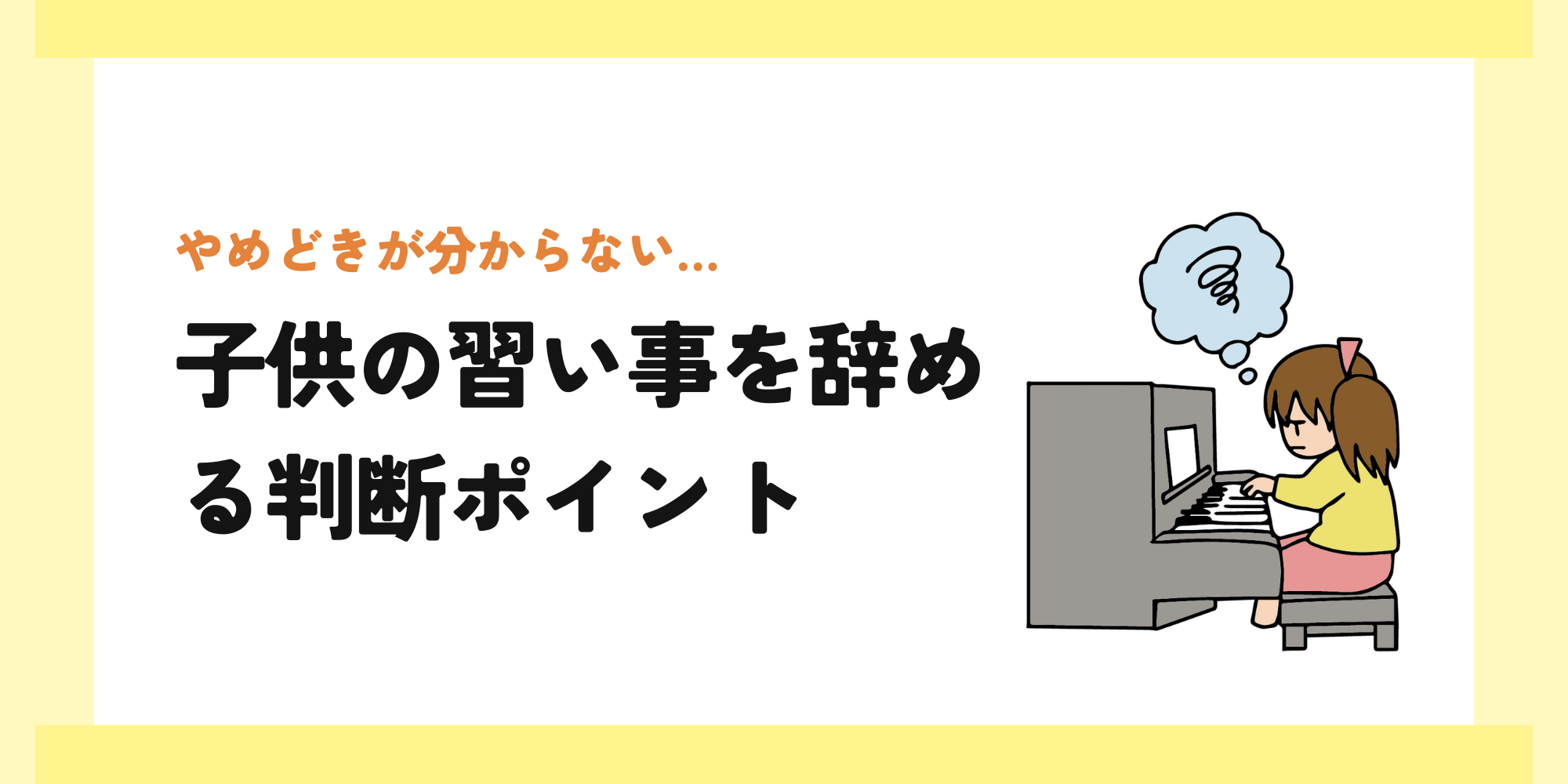子どもの習い事がなかなか続かない、最近になって「行きたくない」と言い出した——そんなとき、親として「このまま辞めさせてもいいのかな?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
せっかく始めたのに途中で辞めるのはもったいない気もするし、「飽きっぽい子」になってしまわないかと心配になることも。でも、無理に続けさせることで、子どもにとって逆効果になる場合もあります。
この記事では、習い事の「やめどき」を見極めるポイントや、辞める・続けるを判断するためのヒント、子どもへの伝え方まで、親目線で分かりやすく解説していきます。
習い事の「やめどき」に多い親の悩み
子どもの習い事を辞めるかどうか判断するとき、最も悩むのは保護者自身かもしれません。
「せっかくお金と時間をかけて始めたのに、ここでやめたらもったいない」
「すぐに辞めさせたら“根気がない子”になってしまうのでは?」
「本当は辞めたいのか、ただ甘えているだけなのか分からない」
そんな風に、子ども本人の意思と親の期待がかみ合わず、迷いが生じる場面は少なくありません。
また、周囲の家庭と比較して「他の子は続けているのに…」と焦ったり、家計への負担や送り迎えの疲れから、内心では「辞めてくれたら楽なのに」と思ってしまうケースも。
親としてどの判断が正解なのか見えづらくなるのが、“やめどき”の悩ましいところです。
習い事を辞める判断ポイント7つ
子どもの習い事を「やめるべきか」「もう少し様子を見るべきか」で迷ったときは、以下のようなポイントを参考にしてみてください。感情だけで判断するのではなく、客観的なサインを見極めることが大切です。

1. 子どもが継続的に強く拒否している
一時的な「今日は行きたくない」ではなく、毎週のように嫌がる/泣く/無言になるなどが何週間も続く場合は、無理に続けさせるメリットよりも、ストレスの方が大きくなっている可能性があります。

2. 心身に不調のサインが出ている
習い事の前になると腹痛・頭痛・不機嫌になるなど、体調や精神面に影響が出ている場合は要注意。表面的には元気でも、「行く前になると不安そう」「眠れない」といった変化があるときは、すぐに見直しを検討しましょう。

3. 目に見える成長や達成感がなく、本人も自信を失っている
一定期間続けても「できるようになった」「楽しい」といったポジティブな感情が子どもから感じられない場合は、達成感を得られていない状態かもしれません。「どうせ僕には無理」「つまらない」などの発言が増えていないか確認してみましょう。

4. 習い事の目的が曖昧になっている・ズレてきた
始めた当初は「楽しく体を動かしてほしい」だったのに、今は競争中心のクラスに変わってしまった…など、目的と実際の活動内容がズレてしまっているケースもあります。本人の興味が別の分野に移っていることもあります。

5. 学校や家庭生活に悪影響が出ている
習い事の疲れから宿題ができない、夕食や入浴が毎回バタバタする、家族との時間が削られるなど、生活リズムに無理が出ている場合は、いったん立ち止まって見直すタイミングです。

6. 金銭的・時間的な負担が大きくなっている
月謝・道具代・交通費など、習い事によっては出費がかさむものもあります。また、保護者の送り迎えや付き添いに毎週数時間取られてしまうと、家庭全体のバランスが崩れることも。家庭の負担と継続の価値を冷静に見極めましょう。

7. 本人に目標や楽しみが感じられなくなっている
「〇〇ができるようになりたい!」「次の発表会が楽しみ!」といった前向きな気持ちが完全に消えている場合は要注意。継続の原動力となる“内発的な動機”が失われていれば、無理に続けても良い結果は生まれにくいでしょう。
辞めること=悪いこと、ではありません。むしろ、本人の気持ちや状況を受け止めて納得のいく形で区切りをつけることが、次のステップにつながります。これらの判断ポイントを参考に、親子でしっかり話し合い、後悔のない選択ができるようサポートしてあげましょう。
一時的な“嫌”との見極め方
子どもが「もう行きたくない」と口にしたとき、それが本心なのか、それとも一時的な気分なのかを見極めるのは難しいものです。
特に幼児〜小学生は、自分の気持ちを正確に言葉で伝えるのがまだ苦手なため、親の観察力と冷静な対応が重要になります。
一時的な「行きたくない」の例
- 発表会や試合など、大きなイベントの直前
- 友だちとのケンカがあった直後
- 疲れている・眠い・他に遊びたいことがある日
- 習い事以外の生活でストレスがたまっているとき(学校・家庭)
こういったケースでは、数日たつと「やっぱり行きたい」と気持ちが戻ることも少なくありません。
見極めるための3つのポイント
- 「いつも」嫌がる?それとも「たまに」?
→ 特定の日だけか、毎回なのかを観察しましょう。 - 習い事が終わった後の様子は?
→ 行く前は渋っていても、終わった後に楽しそうにしていれば一時的なものかも。 - 子ども自身が理由を説明できるか?
→ 「何が嫌だったのか?」を時間を置いて静かに聞いてみましょう。内容が明確でなく、「なんとなく嫌」と言う場合は、一過性の感情のことも多いです。
すぐに結論を出さず、“様子を見る期間”を設ける
判断がつかないときは、1〜2週間ほど様子を見ながら観察期間を設けるのもひとつの手です。スケジュールに余裕がある場合は、1回だけお休みさせて、気持ちの変化を見るのも良いでしょう。
子どもの“嫌”に振り回されるのではなく、継続と見直しの両方を冷静に判断することが大切です。
声かけ例
習い事を辞めるかどうかの判断に親が関わる場合でも、子ども自身が“納得して終われる”ような声かけがとても大切です。無理に続けさせるのも避けたいですが、辞めることを“失敗”と感じさせない工夫が必要です。
前向きに伝える声かけの例
- 「今までよく頑張ったね。〇〇が続けられたことはすごいことだよ」
- 「一度やってみたからこそ、向き・不向きが分かったね」
- 「辞めるっていう選択も、自分のことをちゃんと考えた証拠だよ」
- 「ほかにやってみたいことがあるなら、一緒に探してみようか」
子どもが自信をなくしたり、「どうせまた辞めちゃう」と思わないように、“やってきた経験”を認める言葉がけがポイントです。
続ける場合の励まし方
習い事を続ける判断をした場合は、ただ「頑張って!」と励ますだけではなく、子どもが自分のペースで前向きになれる環境づくりが大切です。
励まし方のポイントと言葉がけ例
- 「うまくいかない日があっても大丈夫。続けてるだけですごいことだよ」
- 「前よりちょっとできるようになったところ、ママ見てたよ」
- 「しんどい時は休んでもいいよ。応援してるからね」
また、レッスン後に「今日どうだった?」と感想を聞いたり、小さな変化や頑張りを具体的に褒めることも効果的です。
“できたこと”に注目してあげると、自己肯定感が育ちやすくなります。
無理にポジティブにさせようとするのではなく、「見守りながら信じているよ」という姿勢を伝えることが、子どもにとって大きな支えになります。
習い事が好きじゃないけど惰性で続けている場合
子どもが「別に楽しくないけど、なんとなく続けている」という状態に陥っている場合、“やめたい”と明確に言わないために親も気づきにくく、対応が難しくなることがあります。
このようなケースでは、以下のようなサインが見られることがあります:
- 習い事の前後でテンションが低い
- 成長や目標への関心が薄く、練習も消極的
- 「行きたくない」とは言わないが、感情がこもっていない
この場合、「やめる・続ける」をすぐ判断するのではなく、いったん立ち止まって“本音”を引き出す対話の時間を設けることが大切です。
「せっかくここまで来たのに…」という親の気持ちもあるかもしれませんが、“頑張ってきた過程”を一度振り返ることで、子ども自身が納得のいく判断をしやすくなります。
続けるにせよ、辞めるにせよ、気持ちを整理する機会をつくることが、惰性を断ち切る第一歩です。
習い事の目的を再設定する方法
習い事を始めた当初は明確だったはずの目的が、続けるうちにぼやけてしまうことはよくあります。
「上達したい」「楽しそうだから始めた」など、最初の動機が薄れたと感じたときは、子ども自身の今の気持ちに合った“新しい目的”を一緒に見つけることが効果的です。
目的再設定のステップ
- 過去を振り返る質問をしてみる
「最初にやってみようと思ったきっかけって覚えてる?」
「前に楽しかったこと、何かあった?」 - 今の気持ちにフォーカスする
「最近ちょっとつまらなく感じるのはどんなとき?」
「このまま続けると、どんなことができるようになりたい?」 - “小さな目標”を一緒に立てる
例:「〇〇の曲が弾けるようになる」「次の大会に出る」など
→目先の成果に集中できると、モチベーションが戻りやすくなります。
目的が「楽しい」「誰かに褒められたい」などでも構いません。本人が“やらされている”のではなく、“自分で選んでやっている”という意識を持てるようサポートすることが大切です。
まとめ
習い事の“やめどき”に正解はありませんが、大切なのは子どもの気持ちや様子にきちんと目を向け、親子で納得できる形で決断することです。
無理に続けることで自信を失うよりも、一度立ち止まり、目的を見直したり、新しい選択肢を考えることが、次の成長につながることもあります。「やめる」「続ける」だけでなく、「どう関わるか」も含めて、子どもの今とこれからに合ったサポートをしていきましょう。